3.誤嚥を防ぐための食事
誤嚥を防ぐためには、一人ひとりの状態に合わせた、食材の選び方や調理方法が必要になります。
介護する家族では判断が難しいと思ったときは、ケアマネジャーや、かかりつけ医、訪問看護師、管理栄養士など関係者に相談してみましょう。
誤嚥しやすい状態とは
次のような状態のときは誤嚥が起こりやすくなります。
- 認知症などにより食べ物が認識しづらくなっている、意識がはっきりせずうとうとしている(先行期の例)
- 歯がなかったり、噛む力が低下している。食べ物が口の中でばらけてまとまらない(口腔準備期の例)
- 舌の動きが弱くなっている、口腔内やのど神経の麻痺がある。のどの奥に食べ物が残っている(口腔期の例)
- 気管の入り口の開閉がうまくいかない、飲み込む動作の前に気管に流れ込んでしまう(咽頭期の例)
誤嚥しにくい食材を選ぼう
高齢者にとって食べにくい食材
-
パサパサ
-
パサつきやすい

パン、芋類など
-
サラサラ
-
むせやすい

水、お茶など
-
ボロボロ
-
ばらけやすい

ご飯、かまぼこなど
-
薄い
-
張り付きやすい
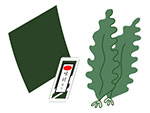
海苔、わかめなど
-
粘り気が強い
-
喉に詰まりやすい

お餅など
-
噛み切りにくい
-
砕いたりすりつぶせない

タコ、イカなど
食材には、嚥下しやすいものと、
そうでないものとがありますので
参考にしてください。
嚥下しやすい食品
▼表は左右にスクロールできます。
| 性質 | 特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| つるんとしている |
|
プリン、ゼリー、絹ごし豆腐、 茶碗蒸し |
| 適度なとろみがある |
|
ポタージュスープ、おかゆ、 アイス、ヨーグルト |
| 適度な粘りがある |
|
バナナ、桃、メロン、生卵、 とろろ |
嚥下しにくい食品
▼表は左右にスクロールできます。
| 性質 | 特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| 噛み切りにくい |
|
たけのこ、ごぼう、いか、たこ、 すじ肉 |
| パサパサ・ 張り付きやすい |
|
パン、餅、クッキー、せんべい、 海苔、もなか |
| サラサラ・ むせやすい |
|
水、お茶、ジュース、牛乳、 酢の物、レモン、梅干 |
| ばらけやすい |
|
そぼろ、ひじき、ナッツ類、 かまぼこ、れんこん |
| 液体と固体が 混在している |
|
味噌汁、お茶漬け、麺類、 ミカン、すいか |
誤嚥予防に「刻み食」は間違い!?
通常の食事が食べにくくなった高齢者に対して「刻み食」であれば食べやすい、誤嚥もしにくいと思いがちではないでしょうか。
刻み食は何のため?
噛む力が低下したり、歯がない人が食べやすくするための工夫の一つです。
刻み食のメリット
食べ物を噛み砕く負担を少なくすることです。
刻み食のデメリット
- デメリット1
刻んだ食材は口の中でパラパラになってしまい、うまくまとまりません。そのため飲み込んでも咽頭に残る場合があり、そのまま気道に食べ物が入りこみやすく誤嚥の原因になることがあります。
対応方法 刻んだ食材にとろみをつけると、まとまりやすくなります。
- デメリット2
噛むことは唾液の分泌をうながします。食材を細かく刻むことで噛むことを省いてしまうと、ますます唾液の分泌量が減り、食材がまとまらなくなる悪循環に陥ってしまいます。
また、噛むことを止めると唾液の分泌量だけでなく、咀嚼筋や舌の動きも低下しがちです。対応方法 細かく刻まなくても食べられるように、舌でつぶせる程度まで柔らかく調理します。
調理を工夫して
飲み込みやすくする!
飲み込みにくい食材は下記のような工夫をして食べるようにします。
押しつぶして柔らかくする
食材を煮込んだり蒸したりすると柔らかくなります。
芋類など押しつぶせる物はたくさんあります。
つるんとした食感にさせる
ゼラチンなどで固めることで、口の中でばらけにくくなります。
ごぼうやれんこんなどはすりおろした後固めます。
つなぎや油脂でまとめやすくする
小麦粉や卵を利用し食材をまとまりやすくしたり、マヨネーズ和えなど食材を和えると飲み込みやすくなります。
また、山芋のようにとろとろした物も和えるのに適した食材です。
とろみをつけて
口の中でばらけるのを防ぐ
食材にあん風のとろみをつけるとばらけにくく、のどごしもよくなります。
嚥下の強い味方「とろみ」
飲み込む力が衰えた人には「水」は危険
水のようにサラサラした飲み物は流れが早く、ばらけやすいため、飲み込む反射が遅くなっているような人には誤嚥しやすい飲み物です。そうしたものは「とろみ」を加えて粘度をつけ、飲み込みやすい形にします。
とろみ剤(とろみ調整食)は、いろいろな種類がありますので、取り扱い説明書を読んで選ぶようにしましょう。また、近年は「とろみ付き飲料」や「とろみボタン付き」の飲料自販機も設置されているところもあります。
嚥下障害があっても、どの部分の動きが悪いかによって、適切な粘度は違います。まずは薄いとろみから始めて、本人に合ったとろみ具合を探しましょう。
分からない場合は、ケアマネジャーや、かかりつけ医、訪問看護師、管理栄養士など関係者に相談してみましょう。
1.薄いとろみ
- スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる
- ストローで容易に吸うことができる
2.中間のとろみ
- スプーンを傾けるととろとろと流れる
- ストローで吸うのは抵抗がある
3.濃いとろみ
- スプーンを傾けても、形状がある程度保たれ、流れにくい
- ストローで吸うことは困難