公的介護保険を利用して住宅改修をしましょう!
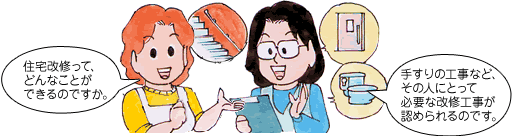
介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5に認定され、身体の状況と住宅の状況に対して必要と認められた場合に、市区町村から住宅改修費が支給されます。
住宅改修の項目
(1)手すりの取り付け
廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりのほか、外へ出るための
(2)床段差の解消
敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。廊下や浴室全体の床位置を上げたりすることで段差を解消する場合もあります。
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室の畳をフローリング材にしたり、浴室を滑りにくい床材にしたり、道路までの通路を移動しやすい舗装材へ変更したりするときに適用されます。
(4)引き戸等への扉の取り替え
開き戸を、引き戸や3枚引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合のほか、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去に適用されます。
(5)洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を、洋式便器に取り替える場合等に適用されます。
(1)~(5)に付随して必要となる工事
手すりを取り付けるための壁の下地補強、床材変更のための下地の補修や
給付金額
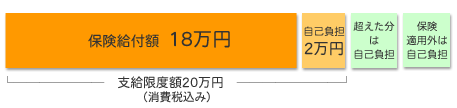
介護保険では、要支援1・2の人も、要介護が1~5の人も住宅改修のための給付は共通で、上限20万円までの1割(※1)に当たる金額が、自己負担となります。例えば改修費が10万円かかった場合は、1割(※1)に当たる1万円の自己負担がかかります。一度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて給付を受けることもできます。
また、要支援、要介護認定区分が、3段階以上あがった時(例:要介護1の人が4になった場合など)か転居した場合は、改めて上限20万円までの給付を受けることができます。
ただし、住宅改修は事前申請制度ですので、改修工事を行なう前に市区町村の介護保険担当部署に申請をしなければなりません。
※1一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。
※公的介護保険制度等に関する記載は2018年11月現在の制度に基づくものです。