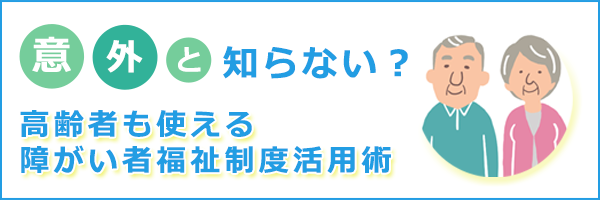車いすの選び方
身体が不自由な高齢者にとって、車いすは単なる移動の手段ではなく、一日の多くの時間を過ごす場所でもあります。身体に負担をかけずに、いかに快適に乗り続けられるか、利用者の身体状況、使用環境、使用目的また介護状況を考慮して選びたいものです。
1.利用目的・身体状況と
車いすの機能
車いすは利用者の身体の状況はもちろん、どこでどんなふうに使うか、使用する目的によって必要となる機能が異なります。生活シーンを想定して選びましょう。
車への積み下ろしが多い
- 折りたたみ
- 軽量タイプ
背もたれ(バックサポート)が折れ、小さく折りたたむことができるので、収納・持ち運びに便利です。

立ち上がりが困難
- スイングアウト機能
- 肘掛け跳ね上げ機能
脚部が横に開き、前方からの移乗が楽に行なえます。立位が困難で、座位移乗を行なう方に適しています。

膝関節の可動域に制限がある
- エレベーティング機能
脚部の上下角度が自由に変えられます。膝関節の可動域に制限がある方に適しています。
円背の方
- 背シート張り調整機能
円背の方で脊柱の凸部はバックサポートにぶつからないよう、円背にそった張りの調整ができます。

長時間の座位がとれない
- フルリクライニング

背もたれの角度を変えることができ、座面にかかる体圧を分散させます。
フルフラットまでリクライニングするので、寝たきりで重度の方の利用にむいていて、簡易なストレッチャーとしても使用できます。
- ティルティング

背もたれ(バックサポート)と座面の角度が一定のまま後ろに傾斜し、姿勢を安定させます。自分では全く身体が動かせない場合、車いすに長時間座っていると床ずれが発生することがあります。このティルティング機能などを利用することにより、お尻にかかる体圧を分散させ、床ずれを防止することができます。
2.身体にあった車いすの選び方
車いす選びは靴選びと同じです。足にあわない靴では歩きづらいように、身体にあわない車いすは使いにくいだけでなく身体機能に悪影響を与えます。利用者の身体にあった車いすを選びましょう。
良い車いすの条件はつぎの3点です。
- 座りやすい(または姿勢保持ができる)
- 移乗しやすい
- 移動しやすい
座面の幅
座って、介助者の手が両サイドに入るくらいの幅。オムツや着衣によって異なりますが、お尻の幅プラス4cmが目安と言われています。
脊椎損傷など障がいによっては体幹が傾かないよう、ゆとりのないぴったりとしたものを選ぶ場合もあります。
背もたれの高さ
脇の下のラインが目安。肩甲骨の下まであることが基本です。
首が座らない人はヘッドサポート付きの車いすをおすすめします。クッションを使用するときは、その厚みも考慮しましょう。

座面の奥行き
背もたれにお尻をつけて座って、膝の内側が少し出るくらい。お尻の後ろから膝の裏までの長さから5cmくらい短いものを選びます。
あまり奥行きが深いと膝裏が座面にぶつかるため、いわゆる「ずっこけ座り」の原因になります。

肘掛け(肘パッド)の高さ
肘を無理なく曲げて乗せられる程度の高さ。座る面から肘の高さを目安に2~3cm高めがよいでしょう。
クッションを使用するときは、その厚みも考慮しましょう。

座面の高さ
足の裏から膝裏までの長さ(座位下腿長)より約5cmほどプラスした高さが立ち上がりやすく座りやすいと言われています。ただし、足こぎをされる方はそれより低めの、下腿長に約1~2cmプラスした高さが適しています。
クッションを使用する場合はその厚みを考慮しましょう。

- 両足こぎの場合
両足のかかとが床に着く高さ以下が適しています。 - 片足こぎの場合(片麻痺の方が片手、片足で操作する場合)
健側のつま先が床下に着く高さが適しています。
3.車いすの付属品の選び方
車いすの付属品とはクッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの。
具体的には以下のものです。
車いす用クッション
車いすの多くは座面がフレームに布を張っただけなので長時間利用するには適しません。そこで適切なクッションが必要です。クッションの素材はウレタンフォーム、ジェル、除圧効果の高い空気入りクッションなどがあります。
クッション・パッドを置くと座る高さが変化するので、車いすと同時に選び、適合させたほうがよいでしょう。身体に変形や床ずれのある場合は医療機関と相談し、床ずれ防止機能の高いクッションやパッドを選びましょう。
電動補助装置
自走用や介助用の車いすに装着して駆動を補助する電動装置。強度面で適応しない機種もあるため、利用している車いすに取り付け可能かどうかチェックが必要です。車いすに取り付けて、車いすを押す・こぐ負担を軽くする目的で使用します。
バッテリーは短時間で充電できますが、容量は大きくないので、長時間の使用は不向きです。
車いす用テーブル
物を置いたり、飲食ができるテーブル。アームサポートの上に固定して使用します。車いすにしっかり装着できるか、利用者の腹部に当たったり、使用するうえで不便はないか、また使用しないときは簡単に取り外しができるかどうか確認しましょう。
車いす用ブレーキ
片麻痺などで普通に装着されているブレーキに手が届かない場合に用いる延長ブレーキ、坂道を上がるときなどハンドルから手を放しても車輪が逆回転しない逆転防止用のブレーキなどオプションで使用します。
4.介護保険法による福祉用具貸与
車いすおよび付属品をレンタルする場合
介護保険サービス事業者に指定された貸与事業者からレンタルします。自己負担は1割(※)です。
購入する場合は公的介護保険の対象外
購入する場合は全額自己負担です。全国の介護ショップ、百貨店、車いすメーカーなどで購入します。
※一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。
2割または3割負担となる判定基準については、2割・3割負担判定チャートをご確認ください。
5.障害者総合支援法による交付
車いすは障害者総合支援法による補装具交付の対象となっています。身体障害者手帳取得者で、車いすが必要と認められた方に交付されます。申請は市区町村の担当窓口。都道府県・政令指定都市の更生相談所の判定を経て、市区町村の交付判定により、業者に発注することになります。
取材協力・写真提供:株式会社 松永製作所