5.グループホームでの実践例
1.認知症高齢者のグループホームでの実践から
グループホームとは、小規模単位の共同生活の場です。家庭的な雰囲気の中でスケジュールを決めず、できるだけ個人の尊厳を守り、一人ひとりのペースに合わせてケアを行ないます。
入居者とスタッフが一緒に食事を作ったり、洗濯物をたたんだり、"普通の生活"の場として入居者ができることを、スタッフが共に手伝いながら生活をする場です。
グループホームが小規模であるということは、入居者とスタッフが互いに身近な存在であるということでもあります。
このグループホームでの回想法を行なう利点は、小規模であるからこそ入居者もスタッフも密着した関係のなかで思い出を語り、聞くということから充実した時間を共有でき、入居者のこれまでの歴史、体験をより深く理解し、日常の援助につなげていくところにあります。またケアの質を高めていくということにもつながっていきます。


これらを背景にグループホームでの回想法実践の様子を述べてみます。
週1回、全8回のセッションとし、各回のテーマをスタッフで検討しました。
入居者にとっては初めての経験ということで、好きなことをおしゃべりする、思い出を語る、お楽しみ会として午後のおやつの時間を含めて1時間(午後2:30~3:30)を設定しました。
入居者の居室から離れた明るい静かな部屋に花を飾り和やかな雰囲気をつくり、やさしい音楽を選んでメンバーを迎える用意をしました。
当日は、どのメンバーからも「何をするのだろう」との不安と緊張の様子が見られました。
参加簿は、きれいな色を組み合わせて作り、参加した回ごとにご自分でシールをはっていただきました。スタッフの手助けを必要とする方もいらっしゃいました。
歌うことの好きなメンバーには、「会の始まりの歌」を毎回歌っていただきました。声を張り上げて真剣に歌う様子に、ほかのメンバーは大きな拍手をしていました。
しかし、その方も、気分の良いときばかりではありません。下を向いてかたくなな態度で歌うことを拒否したこともあります。
このとき、ほかのメンバーが肩を抱き、歌うように促すという光景が見られました。メンバーの支えとともに、注目されていることを感じとって、自分に課せられた役割を果たすこともありました。
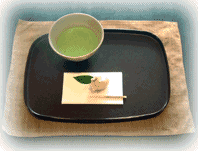

この歌を上手に歌った方は、その後亡くなりました。メンバーのひとりは「○○さんが亡くなってしまった。でも、大きな明るい声でいつも歌ってくれたね。人は亡くなっていっても、ああやって自分を残していくんだね」と言いました。
こう語った人は、日常の場面では、しばしば妄想の状態が現れる方です。しかしこのように、亡くなった方は、残された人の心に思い出を残していました。
この方が日頃どのように自分自身の「最期の時」を思っていらっしゃるのか推察することはできません。それでも、この時のこの言葉と、穏やかで和らいだ表情から、人としての命に向き合う尊さと気高さを私たちに伝えてくれました。
このように、回想法の実践から、メンバーは、たくさんのことを受け取り、そして、生命のもつ意味を感じとったのではないでしょうか。
2.回想法から学ぶこと
これらの実践のなかで、テーマごとにスタッフはメンバーの語る時代への認識不足を思い知らされたり、メンバー一人ひとりの持つ歴史の意味、重さに圧倒されたりもしました。
人生の大先輩の歴史に触れていくごとに、かかわりの未熟さに、自信を失うこともしばしばでした。
それでも、メンバーが喜びを分かち合い、労わり合う関係が育っていくのを目の当たりにし、この方々の一人ひとりの歴史が社会の歴史をつくり、また、社会の歴史が一人ひとりの人生の歴史にどんなにか多くの影響を与えたのかを知らされました。

スタッフの私たちが、生命のつながりを改めて考えることになりました。
回想法にかかわることで、私たちが、自分自身のこれまでの人生を振り返り、思い出として語っていくことの大切さを学びました。
また、自分以外の人生を受け止めることで感動を共有し、互いに流れる生命の大切さに共鳴しています。
加えて、人は誰でも、特定のものごとに対するこだわり、あるいは関心、興味をもっています。
それは、その人自身、得意なことだったり、反対に断念せざるを得なかったこと、あきらめざるを得なかったことだったりするのかもしれません。心を凍らせるような辛い苦しい体験だったりすることかもしれません。
このこだわりをきちんと受け取りながら話を聞いていくことも大切なことのように思います。


人は自分を語ることによって、他者から理解され、認めてもらいたいという自己承認欲求を持っています。
聞き手は、話し手が語り訴えようとしていることを、言葉にならない気持ち、表情、態度、身ぶりなどの非言語の領域も含めて感じとっていくことが大切です。人はよい聞き手を得ることで、ごく自然に自分の存在価値を確かめていくのでしょう。
思い出を語り合い、そこから生まれてくる人生の深さを感じとっていくことに回想法の意義を見いだすことができます。