第3回 <背景・原因>なぜ、このようなことが起こったのでしょうか?
面会が楽しみであった息子さんは1年半ぶりの面会を実現できました。
見知らぬ外国人職員が母親のOさんの介護をしていることをはじめて知りました。
外国人職員の言動や対応が理解できず、自分の希望が受け入れられなかったことが考えられます。
どうしてこうなった?①
家族と接する時の言葉の壁
息子さんに面会のルールとして飲食できないことを伝える必要はあったが、「だめです」「○○しません」等、自然で一般的な言語表現ではなく、指示的な物言いになっている。
そのため家族に違和感や不快感を与えることになったのではないか?
こんな言い方をしなくてもいいのに...

確認するためのポイント①
外国人介護職員が家族やご利用者に対してどのような接し方、話し方をするか日ごろから確認していたのでしょうか。
家族やご利用者に適した話し方ができていない場合、不快感や不信感が生じる状況になってしまいます。
どうしてこうなった?②
価値観の違いの把握の欠如
家族が外国人介護職員をどのようにとらえているかを確認していなかったのではないか?
外国人が介護しているなんて、
どういうことだ!

確認するためのポイント②
ご利用者やその家族によっては、外国人介護職員からサービスを受けるのは抵抗があるといった声があります。
外国人介護職員に対するとらえ方は年代・生育・生活歴が影響を及ぼすことがあります。
どうしてこうなった?③
外国人介護職員の能力への不安
家族は、外国人介護職員がご利用者とどう接しているか・介助しているのかを、見ていない・聞いていないため不安に思うのではないか?
母はちゃんと
介護されているのだろうか...
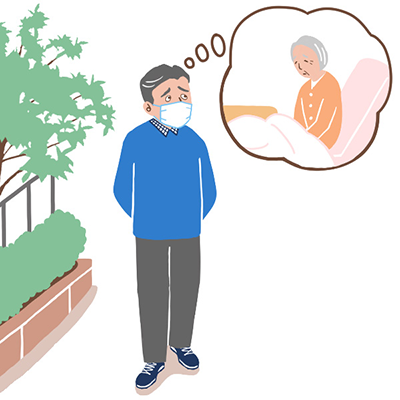
確認するためのポイント③
面会時の家族の様子をみてみましょう。家族の気持ちが把握できるかもしれません。
- 家族が外国人介護職員の介護の様子などを不安そうに見ている
- 日本人介護職員に外国人介護職員の能力についてたずねる